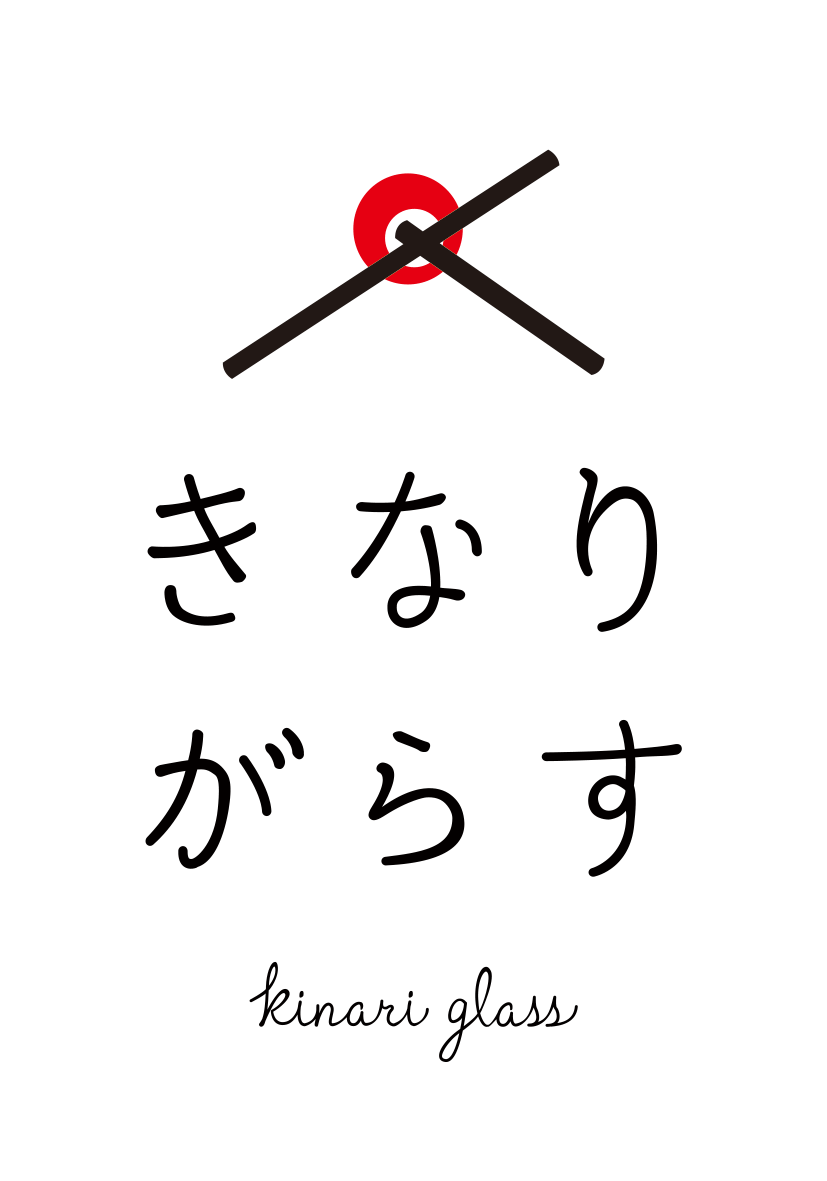自由な輝き
「蜻蛉(とんぼ)玉」なんていかにも工芸品らしいと感じるかもしれませんが、古来より日本のアクセサリーとして愛されてきた穴が開いたガラスの玉(ビーズ)のことです。
ハンドメイドのブームの昨今、このようなガラスビーズを使ってアクセサリーを作る方も増えていますが、この「とんぼ玉」も古くから日本の装飾品として女性たちに愛されてきました。

色ガラスでいろいろな模様をあしらった、穴のあいたガラス玉が「とんぼ玉」と呼ばれていましたが、最近では無地の玉も含めて穴の空いたガラス玉を総称して「とんぼ玉」と呼ばれています。ただし一つ、一つ手作業で作られているものを指すため、同じ形でも機械生産されたものは「とんぼ玉」と言いません。
きなりがらすでも販売しているバーナーさえあれば自宅でもガラスを溶かして好きな形にできます。
アクセサリーを作る人が増えているため、自由に形やデザインを表現できる美しいガラス細工は多くの人を魅了しています。
歴史

名前の由来は、「たくさんの小花のような丸い模様のついたとんぼ玉」が、トンボの複眼に似ていることから、蜻蛉(とんぼ)玉と呼ばれるようになった、と言われることが多いようです。
日本へは奈良時代に製法が伝わってきたと言われていて、その製造の伝統技法は奈良県にある正倉院に製法を記した書物や原料も収蔵されています。
古代、魔除けとして身につけられてきた「勾玉」もとんぼ玉の一種で、装飾品にも使われていたそうです。
このガラス玉が蜻蛉(とんぼ)玉と呼ばれるようになったのは、細かな模様のついたとんぼ玉が「トンボの複眼」に似ていることから名づけられたとの由来があります。
ガラスの発明から間もないころのエジプトで発見されていて、日本でも古い遺跡から勾玉と小型のガラス玉が出土しています。
この美しいとんぼ玉は、現代に至ってもなお愛され続けています。
 ファン式エアバーナーでとんぼ玉製作に使用する花パーツをを作る様子。
ファン式エアバーナーでとんぼ玉製作に使用する花パーツをを作る様子。